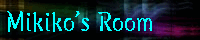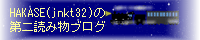轍(わだち)~それから 第30話「計略」
- 2017/01/21
- 11:27

「まあ暫く、飲んだりして話でもしようか」金山副都心での買い物の後、市営地下鉄で居所に戻った中条は、同行の初美にこう言う。「ええ、そうするわ。さっきはちょっと、恥かしかったけど」 「余り気にせん事だよ。まあ、風呂でも・・」 「有難う」
女が入浴の間に、男は、ウチ飲み兼夕食の準備。チーズの類や野菜スティックはいつもの通り。地下鉄を降り、帰りの道中、スマホで注文したシーフードの宅配ピザは、少し小さ目の「M」。首尾よく、彼が支度中に届いた。バス・ローブを纏った初美が上がると、入れ替わりにざっとシャワーのみを浴びる。
乾杯、そして酒食。この夜は、甥 健(たける)の実家に届いた、フランス産赤ワインのお裾分け。産地は確か「ボルドー」と言う地域の「メドック」と言った。同国最大の名産地とかで、風味の奥行きとバランスの良さが秀でていた。「好いわね。ボルドー産は、平均して質が佳くてね。チーズとの相性も、素敵よ」実は、ワインの知識は中条より詳しい、初美も気に入った様子だった。
「こう言っては何だが・・」彼は切り出す。「もう聞くのも嫌かもだが、さっきの一件で、俺たちは小町さんに、言わば『貸し』を作れたと思うんや。これで彼女を、徹君や健に近づけん様にする足がかりが一つできたって、俺は思いてぇんだが、貴女はどう?」
「新(しん)さん・・」初美、静かに返す。「あたしも、似た事を考えてたのよ。そう、健君や徹に、彼女を近づけ過ぎるのは拙いわね。養護主任だから、具合の良くない時、自由に行けないのが辛い所だろうけど」聞いた中条、彼女が、未だに徹を呼び捨てにするのが気になった。「多分・・」男は思った。「去年の夏、彼(やつ)ら二人と交わった時の、記憶の整理がついてねぇんだろうな。特に、徹君とのそれ。今も、微かに思慕でもあるんだろか?」
「初ちゃん・・」少し、酒量の戻った初美に、ワインを代えてやりながら中条。「俺、今まで躊躇(ためら)ってたんだが、今日の今日、去年の『あの記憶』を、無理に消し去る必要はねぇんだよ。そう言うのは、いずれ時が経ちゃ、薄れて行くもんだろうから」 「気遣い有難う。そうね。少しずつ、忘れる様にします」初美も返す。突然の午後の行為、そして、金山へ移動の時の、貨物列車の警音が心に来ている事は、彼も一応は察していたのだが・・
「それでさ」中条は続ける。「仕返しって訳じゃねぇけど、今日の事を、それはそれで覚えといて、小町さんに、あの二人から手を引かせる一つのきっかけにしようと思うんだ。彼(やつ)らはつまり、普通の中坊に戻って、勉強や部活に勤しみてぇって事だ。最終的には、男生徒に、一切手を出させん様に徹底させる事やけど」 初美「それよね。さっきは随分だと思ったけど、そうなんだ。あたしたちも、彼たちを守る事に協力しないとってとこだからね」 「そうそう。ある意味、巻き込んじまって悪いんだが、そんな事もあるもんでね」 「ううん。そう言う事なら、喜んで協力するわ」
「とに角、小町の童貞漁りは、豊(ゆたか)を最後にしなければならない」と言う想いでは、初美も一致していた。佐分利学院の養護主任の座に就いてもうすぐ三年、理事長が黙認しているとは言え、露見せぬ様一定の期間を置いているとは言え、分っているだけで、六人の未成年男生徒に手を出したのは紛れもない事実。もし白日の下になれば、未成年者福祉法規等違反での刑事問責は目に見えているし、学院の名誉にとっても、大ダメージとなる事は明らかだ。
「まあ、一晩であれもこれも話し合うのも疲れるから、今夜はこの辺にしとこう。さて、こっちはどうかな?」中条、こう言いながらTVの電源を入れ、プロ野球中継をチェック。期待に反し、この日の NCドラゴンズは、西日本の某ドーム球場で HEタイガースと対戦、先日に続く劣勢。この所、どうも不調がちの様だ。それよりも・・
中条が「この時季は、高校野球の夏季大会もあるよな。夏の日中の甲子園は、ここの所の猛暑化で大変なんだよな。熱中症とかで倒れる若衆もいるしさ。『根性なし』とかの問題じゃねぇんだ。気象がこうなっちまった以上、夜のプロ試合と入れ替えて、ええ加減にドーム球場試合を認めたらんといかん。なあ初ちゃん」こう言えば、初美も「そうよね。あれは、あたしも見てて辛いわ。昔と違って、これだけ暑いんだから、何とかしてあげないと可哀そうよ」と応じ。この時、偶然二人の脳裏に、国際レベルでの不安が過った。それは、2020年に開催予定の、次回東京五輪とパラリンピックが、まともに開けるのか?と言う疑問だったのだが、それは話題には至らなかった。
「今夜は、もういかんわ・・」今回のプロ野球試合も、芳しくなさそうだ。男は「今夜は彼女に、無理させたくねぇ。何なら、行為なしでも好い位。さっきの対策話ができただけでも、儲けものだったわ」そう思いながら、TVの番組表を見て行く。某民放番組を観ようと決め、chを合せた所へ、着替えた初美が現れ、右隣に座る。去年の夏、彼を挑発した時と、それに初めてここを訪れた時と同じ、白のミニコス姿である。
「初ちゃん、やる気か?」気になった中条は、そう尋ね。すると「分らないわ。でも、もう少ししたら、何となくイケそうな気がするの」初美、こう返し。「新さん・・」 「うん、何かな?」 「あたしは、立ち直りの速い女よ。貴方の心配は嬉しいし、有難いけど、そんなに弱くない事も知って欲しいわ」 「う~ん、そうか。痩せ我慢じゃねぇだろうな?」 「そんなのじゃないわ。だから、し・ん・じ・て・・」 「あ~、分った分った。・・は好いけど・・こらこら、手を出すの、ちと早過ぎやせんか?」
会話が一区切りする頃には、中条の穿く トランクスが下にずらされて「彼自身」が露わにされ、初美の、しなやかでなよやかな左手の標的となっていた。陰嚢が白い手指の包囲を受け、虫の様に動き蠢いて、ゆるやかに揉まれる。次に、手指は男根の幹を伝って先端へ。亀頭、そして鈴口の辺りをじっくり、ねっとりと撫で回し、勃起を促す。それは恰(あたか)も「さあ、起立しなさい!この無礼者!」と叱咤している様にも感じられる動きであった。
「ハハ、そうか。無礼者で悪かった。でも俺、今日は一回昇り切っちゃってるんだよなぁ」と中条。対する初美「でも、あれから半日でしょう。もう大丈夫よ、男なんだから」と返し。そうなんだよなぁ。「男でしょ!?」と出られりゃ、それは簡単には退けなくなる。誰でもそうだろうが。「それも有りだな・・」下方を撫でさすられ、弛まぬ刺激を受けながら、男はそう思った。女は、今度は隠し持っていた筆で、彼の陰嚢を刺激して行く。ゆっくりグルグルと、玉袋に当てた穂先を回す様に、感触を高めて行く。それは、ほぼ毎朝、彼の居所の向かい家屋上に現れる Kuso犬の、グルグル回る「気狂い踊り」を見る時の快感に似ていた。
「さあ新さん、もう少し濃い事をするわよ」初美、筆の刺激を止める事なく、次には空いた左手で、礼儀を正した、中条の男根の幹と裏筋から先端へ向け、マッサージを仕掛ける。一度は静まっていた欲求が、再び呼び覚まさせられる様だ。「うう・・、んん・・、は・・初ちゃん。む・・無理はいかんぜよ、ううう・・」強い刺激を受け、男は呻く。「そうそう、そんな感じで、もう少し高まって欲しいわ。ね、もう少しだけ、頑張って・・」女は微笑み、左手の動きを大きくし、更に刺激を加えて行く。「な・・何かさぁ、いつもの夜と変わらんくなって来たぞ。貴女、マジで立ち直り早いな。意外だわ~!」中条は感嘆した。
「ふふ、随分感じてくれた様で、嬉しいわ。さあ、じっくり触らせてくれたから、今度はあたしからご褒美をあげるね。まずは、そう・・キスよ。でも、その前に、言葉が欲しいわ」 聞いた男は、その言葉を察知した。女と目を合せ「初ちゃん、好きだ・・」 「あたしもよ・・」数十秒の間、舌技を交えた、濃い口づけ。そのものは、前と同じだが、この夜は、違うそれに思えた。
「ねえ、そろそろ触りたいでしょう」 「そりゃそうだ。でも、無理はいかんよ」 「大丈夫よ。貴方は、いつも丁寧な出方だって、知ってるから。でも、今夜は胸からね。お尻は後よ・・」 「あ~い、分った。じゃ、上の方からな」中条はこう言うと、初美のキャミソールを下へずらし、ブラをゆっくり外して、顔を出した中庸の「胸の双丘」に顔を埋めて挨拶した。それから、筆使いを交えて、乳房への愛撫を一通り。
もう、少しの事では、初美も喘がなくなった。「慣れるとね、相当な刺激がないと、声が出る所まで行かないの。貴方はどう?」 こう訊かれ、中条は「俺か?相変わらずだよ。さっきなんかも、貴女に玉袋を一擦りされただけで、もうアヘアヘだわ~」と返す。「随分過敏ね、本当かしら?でも、感じられるってのは、健康な証拠よ。もっと仕掛けようかな」女は微笑むと、露出したままの男の一物の先端に、唇を合せ。鈴口に舌先を走らせ、幹から陰嚢へと舐め回して行く。「んん・・好い。何か、いつもより濃い様な気がするな。初ちゃん、本当に立ち直ったんか?」仕掛けられる中条、その脳裏には、まだ一抹の不安が残る・・
(つづく 本稿はフィクションであります)。
今回の人物壁紙 三上悠亜
松岡直也さんの今回楽曲「二人の会社」下記タイトルです。
Futari no Kaisha